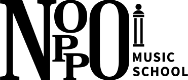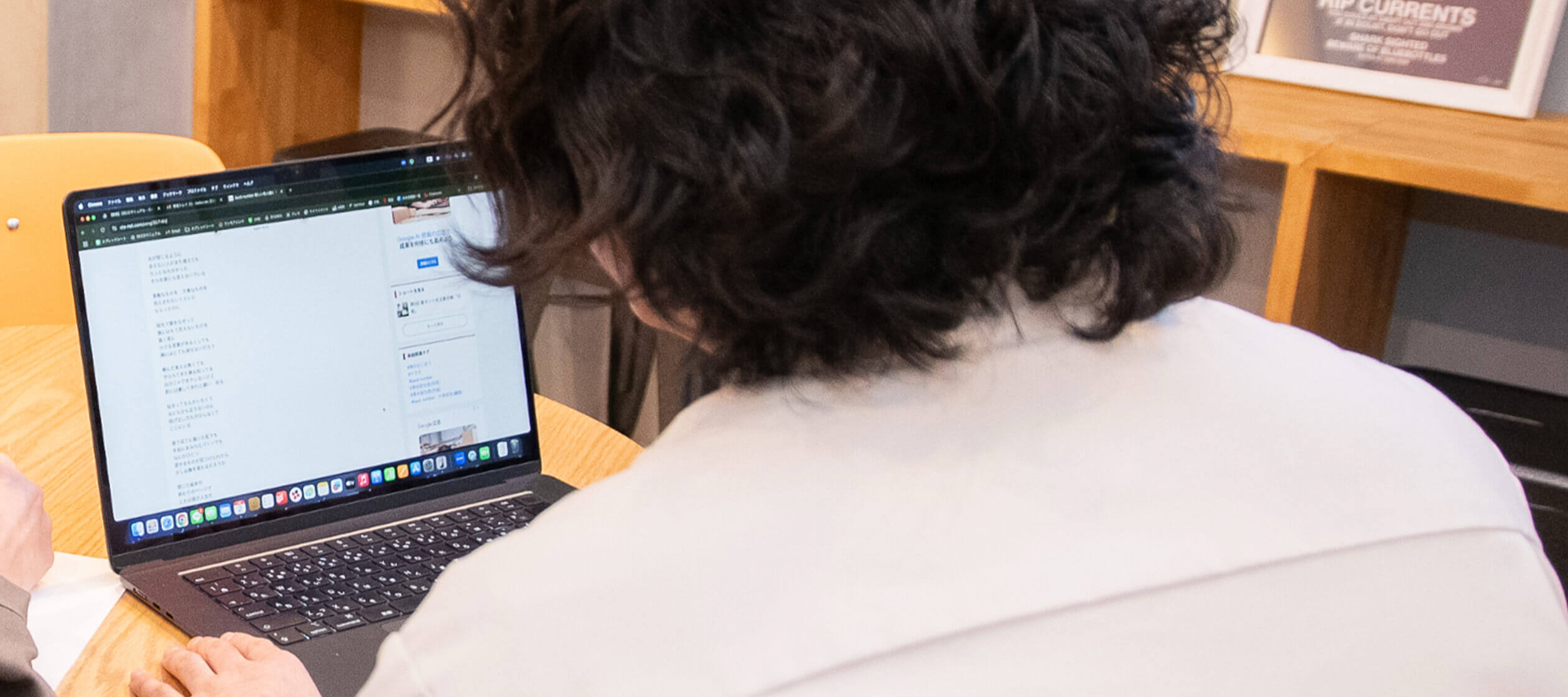こんにちは!
NOPPO MUSIC SCHOOLです!
時折テレビを見ていると、クラシックのコンサートが流れていると思います。
その中でも、ひときわ目立つのは、「オペラ」です。
マイクを使わず、オーケストラに負けない声量で観客を圧倒する姿は、ついつい目を留めてしまいます。
では、オペラ歌手は、なぜあんな歌唱ができるのでしょうか・・・?
そこで今回は。
「オペラ・声楽」の発声方法について徹底解説致します!
仕組みに限らず、ポップス・ミュージカルとの違い、トレーニング方法まで解説しますので、ぜひ活用してみてください!
では、参りましょう!
オペラとポップスの発声の違い
では、オペラの発声は、ポップスを歌うことと何が違うのでしょうか・・・?
オペラとポップスの違いその1~ホールで歌うか、マイクを通して歌うか~
基本的に、オペラはマイクを介さず、そのまま生の声を観客に届けます。
オペラやクラシック声楽曲は、オーケストラやブラス、ピアノといった「生音」を伴奏として歌い上げます。
これには、声楽の始まりが太古よりあり、マイクやスピーカーといった電子機材が誕生するずっと昔から存在していたことが理由として挙げられます。
昔の人は、どうやって音楽を楽しんでいたのか。
起源は宗教音楽にあり、教会で歌われることが多かったのです。
声楽が大衆化されていくごとに、「ホール」や「歌劇場」といった、一度に多くの人が音楽を楽しめる施設が生まれました。
ホールや歌劇場は、より音楽が楽しめるよう、生音がしっかり反響するように作られていることが多く、演奏者はこの共鳴を利用して、観客に音楽を届けることが求められるようになったのです。
この生音同士の共鳴は、スピーカーやアンプを通してだと実現が難しい、独特の音色を生み出すことができるので、近代声楽が成立してから300年以上たった今でも、その価値が見いだされるのです。
屋外でのコンサートでは、反響するものが無く響きづらいので、マイクを使用することもあります。
ただ、口元からは離れ、体全身の共鳴を集音できるような配置になっていたりします。
それに対しポップスは、マイクを通した電子的な音を観客に届けます。
クラシックが共鳴を利用したクリアな音だとしたら、ポップスは普段の話し声に近い、あえてノイズを交えた声になります。
この熱狂的な音をマイクなしに多くの観客に届けるのは、かなり至難の業です。
なので、音を増幅させることのできるマイクが使われるようになりました。
オペラは、「拡散する」、ポップスは、「マイクに集める」。
このような違いが、大きく見られます。
オペラとポップスの違いその2~音楽性の違い~
クラシック音楽は、もともと神様に捧げるためのものであったのもあり、ゆったりとした美しいメロディが特徴的です。
また、とても早いメロディを、超絶技巧で完璧に淀みなく歌い上げることも求められます。
そして、何の歪みもない真っすぐなロングトーンは、観客の心を湧きあがらせることができます。
この歌唱を実現するためには、音楽を丁寧にかつ緻密に、美しく作り上げていくことが必要です。
なので、発声も、音程や音色が寸分狂わない精密なテクニックが必要になるわけです。
ポップスは、ロックやR&B、ジャズ、ヒップホップといった様々なジャンルの複合体だと言われています。
これらのジャンルに必要なのは、聴きなじみが良い、その場にあった多種多様な表現です。
一定の音色を保ち続けるよりも、毎秒変化させて、観客を熱狂させていくことが求められます。
オペラとポップスの違いその3~リズム~
ここが、かなり大きな違いになると思われます。
表拍でとるか、裏拍でとるか。
基本的に、クラシックは表拍でリズムをとり、丁寧に音楽を作っていくことがほとんどです。
逆にポップスは、裏拍でリズムを取ることが多く、観客をリズムに乗せながら演奏していきます。
それぞれ逆にしたときに、音楽に違和感が生じてしまいます。
中には、「カノンロック」といった、音色もリズムもロックの上で、パッヘルベルのカノンを演奏しているものもありますが・・・。
※これはこれで良いマッチになっていますね!
リズムについては、クラシック、ロックやR&B、ジャズ、ヒップホップ、それぞれで特有のものがあるので、演奏するときにしっかり区別することが大切です。
オペラとミュージカルの発声の違い
オペラとミュージカルの発声は、かなり近いところにあるとされています。
ホール全体に響く、拡散する歌唱は両方で求められると思います。
ミュージカルとオペラの最大の違いは「言葉」にあります。
オペラもミュージカルも、歌を用いて物語が進んでいきます。
この時、ミュージカルはセリフもあるので、歌とお芝居が分かれてはいけません。
ミュージカルの歌は、セリフで物語が進んでいった先にあります。
なので、どんな言葉を話しているか、母音や子音をはっきりさせ、明確に伝えることが必要です。
また私たちが日常的に耳にするような自然な声や裏声を活かして歌われます。
その時、役者は歌うだけでなく、踊ったり激しく動いたりしながら演じるため、声をしっかり届けるためにマイクが欠かせません。
オペラの発声をベースにしながら、物語をしっかり伝えられる発声が、ミュージカルにはより求められるわけです。
ミュージカルについて知りたい方はこちら!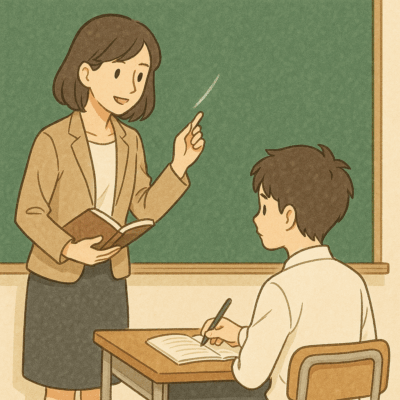
オペラの発声「ベルカント唱法」とは?
それでは、オペラの発声について詳しく解説していきます。
オペラの発声方法の代表的なものが、「ベルカント唱法」です。
「ベル・カント」とは、「美しい声」という意味で、オペラ発祥であるイタリアの伝統的な歌唱方法です。
ベルカント唱法は、無理することなく、周りの空間を響かせることで歌声を届ける発声方法です。
大きくテクニックがあるというよりかは、望ましい歌唱の代表としての、概念的な意味合いでいわれることがほとんどです。
では、どうすればベルカント唱法を手に入れることができるのか。
オペラの発声には、周りを響かせる「共鳴」がカギになっていきます。
身体全身に音が共鳴、共振し、普段の話し声とは違った発声方法を目指す必要があります。
オペラの発声その1~腹式呼吸で、安定した息を~
腹式呼吸とは、腹部にある「横隔膜」を使った呼吸法。
肺を大きく細かく動かし、最大限息を使うことができます。
また、正しく行えると、リラックスした状態でも息を扱えるので、細かい調整にも利用することができます。
では、その息は何のために必要なのか。
これは、声帯をしっかり振動させるためなのです。
声帯とは、「声を出すための器官」
二枚の声帯ひだを震わせることで、息を振動させ、音を作ります。
この時、声帯を最大限振動させるには、「脱力」と「適切な息」が必要です。
頑張って声を出そうとして力んでしまっては、声帯は緊張しすぎてしまい、思うように振動しません。
また、息が少なかったり、また吐きすぎてしまうのも声帯の振動を妨げます。
よって、負荷をかけずに、かつ適切な息の量を調節するためにも、腹式呼吸は欠かせないのです。
オペラの発声その2~共鳴腔を使い、響かせる~
オペラでは、声帯で生まれた声をホール全体に響くように増幅させる必要があります。
この時、「口腔(口の中)」や「鼻腔」に響かせる必要があります。
これを、「共鳴」と言います。
特にオペラでは、「中咽頭」と呼ばれる共鳴腔を利用します。
中咽頭とは、口を大きく開けた時に見える、口の奥にある部分です。
具体的には、口蓋垂(のどちんこ)のあたりから舌の付け根、そして喉の突き当りの壁あたりまで指します。
この部分に響かせることで、オペラ特有の、深い響きを生み出すことができます。
そして、上咽頭と呼ばれる「副鼻腔」や頭部の上側にも響かせることで、より共鳴しやすい明るい響きを生み出します。
これらを複合的に行うことで、声をホールに響かせ、オーケストラを飛び越えて観客に届けることができます。
オペラの発声その3~体に響かせる~
音は波状に広がっていくので、頭部だけではなく体にも響かせる必要があります。
特に、胸に響かせられると、よりしっかりとした音になります。
これを、「共振」と言います。
この時必要なのが、体が「脱力」している事です。
無理に息を送ろうとして体が緊張してしまうと、振動する際抵抗が大きくなり、うまく声を響かせられません。
上手く脱力し、自然と体が共振するよう、声を出していくことが必要です。
ベルカント唱法で歌うオペラ歌手を紹介!
ここでは、ベルカント唱法で歌う世界的なオペラ歌手をご紹介致します!
響き方や体の使い方に着目し、参考にしてみましょう!
ぜひ、聴き比べをしながら、自分の発声と照らし合わせてみてください。
ルチアーノ・パヴァロッティ(1935年~2007年)
プッチーニ作曲 オペラ 「トゥーランドット」より、「誰も寝てはならぬ」
チェチーリア・バルトリ(1966年~)
ヘンデル作曲 オペラ 「リナルド」より「私を泣かせてください」
オペラの発声!レッツトレーニング!
ここでは、オペラの発声を手に入れるトレーニングを解説します!
自身の変化に注目しながら、練習していきましょう!
体の使い方や響き方を丁寧に感じながら進めることが大切です。
オペラの発声トレーニングその1~腹式呼吸~
➀ 姿勢を正し、足は肩幅くらいまで広げ、まっすぐ正面を見つめます。
➁ 手を脇腹にあて、親指は背中に固定します。
※前ならえの先頭の姿勢です。親指は指圧師さんのイメージで腰を軽く押します。
➂ 口から、あくびをしながらゆっくり吸います(4秒)。
この時、手を押し返すように、お腹を膨らませていきます。(浮き輪のイメージで)
➃ 口を少しすぼめ、スーッと音を出しながら、細く長く吐いていきます。(8秒)
息を多く吐くより、圧をかけていくイメージで、長く吐いて下さい。
➄ これを適宜、繰り返していきます。
横隔膜(腹部にある、肺を動かすための器官)は、お腹の前側だけでなく、360度のイメージで腹部にあります。
一部分だけでなく、全体を稼働させてあげるとよりよいトレーニングになります!
以上です!
体全身に力が入らないよう、注意して行いましょう!
オペラの発声トレーニングその2~共鳴腔を広げる~
➀ あくびをするイメージで、口角を上げながら喉の奥を広げるように、口を開けていきます。
➁ 声を「ア~」と出していきます。
この時、前に出そうとせず、真上に柔らかく出すイメージです。
力を入れずに大きく出そうとすると、自然と響く声が出てきます!
➂ そのまま、「ドレミファソファミレド~」と、音程を変えていきます。
出来るだけゆっくり、正確な音程に合わせていきましょう!
➃半音ずつ、キーを上げていきます。
苦しくなったら、「ド」のキーまで下がっていきます。
以上です!
最初は実感があまりなくても、開ける事を意識すれば音色は変化していきます。
空間に響いているかも確認しながら、練習していきましょう!
オペラの発声トレーニングその3~脱力~
上記のトレーニングを行っていて、どうしても力が入ってしまうことがあると思います。
まず、大きく息を吸って、「ハァ~」と息を吐いてみましょう。
上手く力が抜けてきたら、「その2」に練習を、両手を広げ、体を揺らしながら行います。
首も力が入りやすいので、左右に振りながら体を揺らしていきます。
余分な力が抜けるので、声が響きやすくなっていきます!
歌唱による疲れも改善できるので、ぜひ試してみてください!
発声の基礎についてより知りたい方はこちら!
オペラの発声にまつわる、よくある質問
Q.声が小さいと言われます・・・。そんな私でもオペラは歌えますか?
A.歌えます!
最初からオペラ発声ができた人は、そういません。
確かなテクニックを手に入れることができれば、必ず歌うことができます。
まずは、これまでにやったことのないトレーニングから、試してみることが重要です!
声の可能性を、広げていきましょう!
Q.オペラをやってみたいけど、中々踏み込めない・・・。
A.まずは、気軽に声楽のレッスンを受けてみましょう!
オペラにはどうしても、敷居が高い印象があります。
しかし、日本には声楽の講師も多くいて、初心者からでも、丁寧にテクニックを教えてくれます!
まずは、イタリア歌曲や日本歌曲など、挑戦しやすいものがおすすめです!
音源を良く聴き、歌ってみるところから始めてみましょう!
Q.オペラ発声は、ポップスには関係ない?
A.大いにあります!
よりダイナミックな歌唱をするために、特に、のびやかなハイトーンを出したいとき、オペラの発声は良いヒントになります。
共鳴は、オペラの発声だけのものではありません。
ポップスの歌唱でも、歌唱表現に大きくかかわっていきます。
ここで、オペラ発声をポップスに取り入れている歌手を紹介します。
是非、参考にしてみてください!
平原綾香 「Jupiter」(2003年)
オペラ発声で、新しい世界を!
未知のオペラの世界、いかがだったでしょうか。
このコラムで知ったことを、普段の歌唱に織り交ぜるだけでも、新しい自分を知ることができるかもしれません。
また、クラシック音楽を知ることも、ご自身の音楽観に新しい刺激をもたらすことと思います。
ぜひ、新しい扉を開くイメージで、違うジャンルにもトライしてみましょう!
良い歌ライフを!
実際にオペラを歌ってみたい方はこちら!