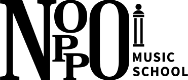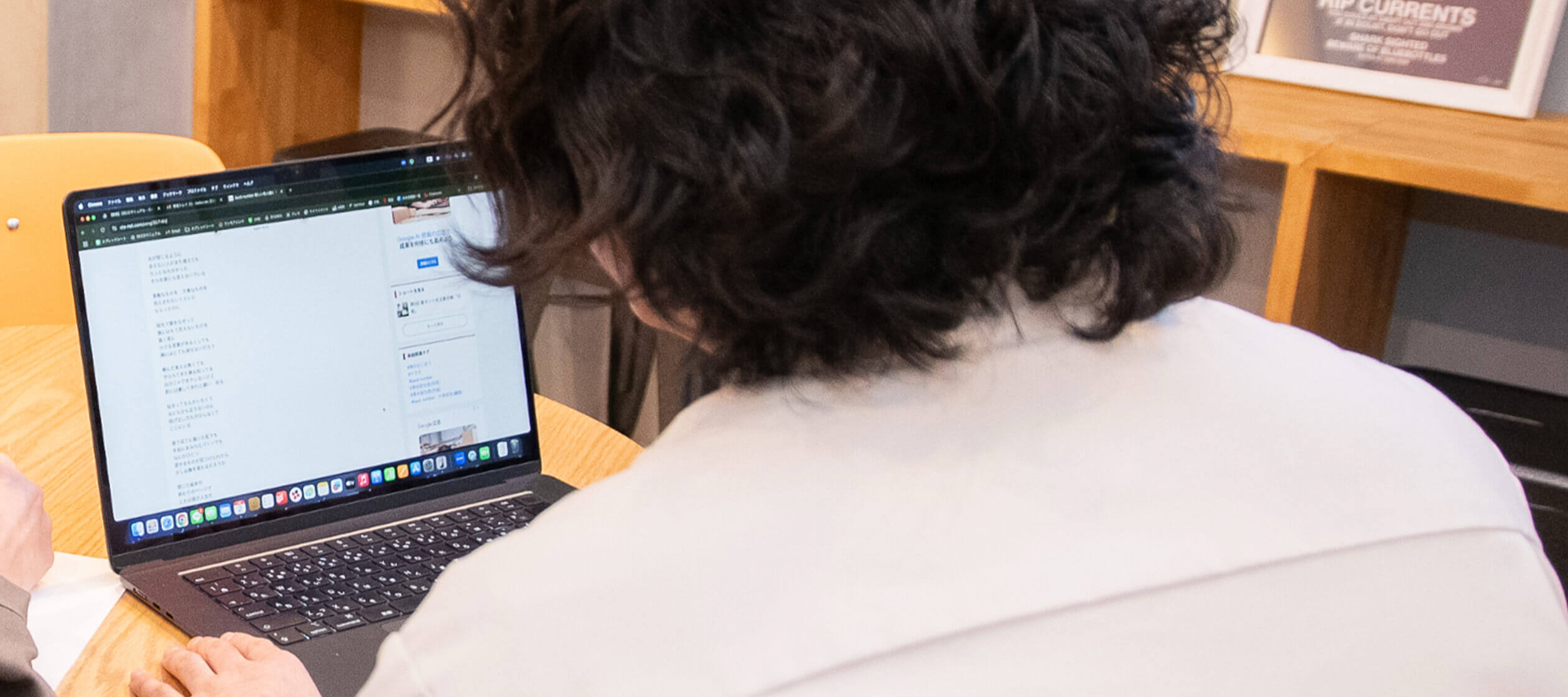こんにちは!
NOPPO MUSIC SCHOOLです!
歌を学んでいる人なら、一度は耳にしたことがある「声帯閉鎖」という言葉
「高音が苦しい」
「息が漏れて弱々しい声になる」
「声がこもって響かない」
そんな悩みの裏側には、この声帯閉鎖のバランスが大きく関わっています。
声帯閉鎖とは、「声帯がしっかりと合わさって声を作る仕組み」のこと。
しかし、単に「閉じればよい」という単純なものではなく、声帯閉鎖は 筋肉の精密な協調 によって成り立ち、歌唱の質や表現力を大きく左右します。
本コラムでは、声帯閉鎖の仕組み、関わる筋肉、歌唱における利点、そしてトレーニング方法について徹底的に解説していきます。
あなたの表現のより良いブラッシュアップに繋がれば、幸いです。
では、参りましょう!
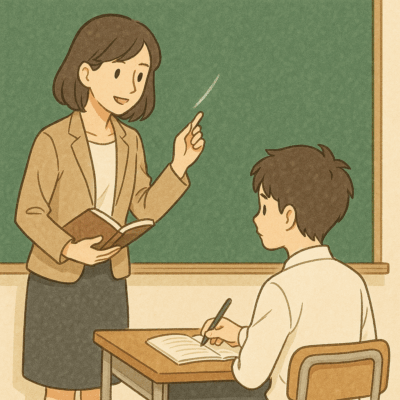
声帯閉鎖とは?
声帯閉鎖とは?➀~声帯の基本構造~
人間の声は、喉頭にある「声帯」の振動によって作られます。
声帯は左右2枚のひだのような組織で、普段は気道を開けるために離れています。
息を吐くときにこれらが閉じ、空気の圧力で振動することで「声」が生まれるのです。
声帯閉鎖とは?➁~声帯閉鎖の定義~
「声門」とは声帯の隙間のこと。
声帯閉鎖とは、この隙間を 適切に閉じる 動きのことを指します。
• 強く閉じすぎる → 声が詰まって喉が苦しくなる
• 弱すぎる → 息漏れのある声になり、力強さを失う
この場合声帯閉鎖を行う上で大切なのが、「バランスよく閉じる力を調整できている事」なのです。
ただ強すぎてはいけませんし、弱いと声になりません。
つまり声帯閉鎖は、「息の効率」と「声のクオリティ」を決める、発声の根幹なのです。
声帯閉鎖に関わる筋肉
声帯閉鎖を上手く行うには、声帯周りの筋肉を意識して稼働させることが必要です。
ボイストレーニングでは、声帯周りのの筋肉を意識し鍛えることで、声のブラッシュアップへと発展させていきます!
声帯閉鎖に関わる筋肉➀~甲状披裂筋~
甲状軟骨と披裂軟骨をつなぐ筋肉。
声帯の内側にあり、声帯を厚く・短くする役割を担います。
声帯閉鎖においては、声帯同士をしっかりと接触させる働きがあり、地声感のある響きを生みます。
声帯閉鎖に関わる筋肉➁~外側輪状披裂筋(側筋)~
声帯の後ろを内側に引き寄せ、声門を閉じる重要な筋肉。
声帯閉鎖に関する筋肉➂~披裂間筋~
「横披裂筋」と「斜披裂筋」を合わせて称され、披裂軟骨を引き寄せ声門を閉じる働きをする筋肉。
この甲状披裂筋、外側輪状披裂筋、披裂間筋の働きをそれぞれ組み合わせ、声帯閉鎖を促しています。
いずれかの筋肉が弱いと声門が閉じきれず、息漏れの声になりやすいです。
声帯閉鎖に関する筋肉➃~輪状甲状筋~
輪状軟骨と甲状軟骨をつなげる筋肉。
高音発声に関わる筋肉。
声帯を引き下げ、薄くさせることで音の振動数が多くなり、声は高くなります。
高音発声時、輪状甲状筋と甲状披裂筋のバランスが崩れると、声帯閉鎖が不安定になります。
より声帯について詳しく知りたい方はこちら!
声帯閉鎖のメリット
声帯閉鎖を適切に行えると、歌唱は劇的に変わります。
その利点を具体的に見ていきましょう。
1. 息の効率が良くなる
声門がしっかり閉じると、息が無駄に漏れません。
その結果、少ない息でも響きが保たれ、長いフレーズも楽に歌えるようになります。
2. 声に芯が生まれる
閉鎖が不十分だと「息っぽい声」になりがちですが、適切な閉鎖は声に芯を与え、ホールで響く力を持たせます。
これは、声帯閉鎖を強くしていくと、音の振幅が大きくなり、声量自体がアップするからです。
これに共鳴を加えると、より良く響かせることができます。
3. 音域が広がる
高音では声門が不安定になりやすいため、閉鎖が甘いと声が裏返ります。
音は振動数が多くなると、高くなります。
高い声を保つには、多い振動数を無理なくキープする必要があります。
息の量では負荷が大きくかかってしまうので、声帯を多い振動数を生み出せる状態に作ることが必要です。
正しく声門を閉じられると、高音でも力強く安定した声を出せます。
4. 表現力が増す
声帯閉鎖の強弱をコントロールすることで、
• 息の混ざった柔らかな声
• 力強く押し出す声
• 透明感のある裏声
• 芯のあるハイトーン
など、多彩なニュアンスを表現できます。
これらを楽曲に合わせて使い分けられることが、表現力アップには必要です。

声帯閉鎖のやり方
ここでは、声帯閉鎖のやり方をご紹介します!
ぜひ、感覚として掴みやすい方法を実践してみましょう!
声帯閉鎖のやり方~息を止める~
声帯閉鎖の感覚を掴むとき、息を止めるという方法があります。
試しに、軽く息を止めてみましょう。
この時、喉の周りが緊張すると思います。
このまま、息を抜かずに声を出してみましょう。
すると、じりじりとした苦しい時の声が出ます。
これが、過度に声帯閉鎖している時の声です。
そこから少しずつ息を抜き、ある程度操作が効く声になったら、歌っていきます。
普段より息成分の少ない、芯のある歌声になったら、上手く声帯閉鎖出来ている証拠です!
もし感覚が難しければ、声を低音で「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛」と鳴らす「エッジボイス」の練習で声帯閉鎖の感覚を掴んでみましょう!
声帯閉鎖のトレーニング!!
では、声帯閉鎖を鍛えるトレーニングを解説致します!
脱力をイメージしながら、適切に筋肉を鍛えていきましょう!
声帯閉鎖を鍛えるトレーニング➀~リップロール~
唇をブルブル震わせながら声を出す練習。
息と声帯のバランスを整え、自然な閉鎖を促します。
表情筋のトレーニングにも効果的!
➀両手の人差し指で両側の方を引っ張りながら、唇を「ぷるぷるぷる・・・」と震わせるように息を吐いていく。
➁慣れてきたら、声を同時に出していく
➂スケール(ドレミファソラシド)に合わせ、リップロールをしながら音程を取っていく。
➃低音から高音へと、移動させていく。
力みなくできるようになれば、コツをつかめている証拠!
焦らずやっていきましょう!
声帯閉鎖を鍛えるトレーニング➁~エッジボイス~
ごく少ない息で「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛」と声帯を鳴らす練習。
自分の中で、一番低い音を出すイメージです。
閉鎖筋を目覚めさせ、必要最小限の閉鎖感を体感できます。
➀リラックスしながら、「あー」と声を出す。
➁ゆっくり音程を低くしていき、自分が出せる最低音まで持っていく。
➂息漏れのない、ガラガラした声に近づけていく。
➃息が切れるまで、ムラなく一定に声を出し続ける
胸に手を当て、「共振」(胸などの体に響くこと)ができているか確認しながら行うと効果的です。
力みがあると、エッジボイスはうまくいきません。
声帯がしっかり閉じられ、振動しているか確認しながら行いましょう。
声帯閉鎖を鍛えるトレーニング➂~「ネイ」での発声~
「い」の母音で、音階(スケール)で練習していきます。
「い」に母音は声門閉鎖を促しやすく、響きを実感しながら練習することができます。
➀「ド」の音から始め、同じ音で3回「ネイ、ネイ、ネイ・・・」と発声していきます。
➁「ドレミファソラシド」と、1音ずつ上げて行きます。
➂慣れてきたら、5トーン(ドレミファソファミレド)で発声していきます。
この時、音が途切れないように繋げて発声していきましょう。
➃キーを上げていきます。苦しくなったら、無理のない高さで元の音に降りていきましょう。
この時、口を開きすぎると息が漏れ、声帯閉鎖が上手くできません。
音が濁ったり、苦しくなったりする場合は、声帯閉鎖しすぎている状態なので、脱力を心掛け、一番響く感覚を身に付けていきます。
もし閉鎖が苦手な方は、鼻の下(人中)に声を当てるイメージ声で行ってみてください!!
声帯閉鎖を実感しやすくなります!
高い声をかっこよく出したい方はこちら!
声帯閉鎖をトレーニングする上での注意点
声帯閉鎖をトレーニングする上での注意点➀~閉じすぎないこと~
「閉鎖=力む」ではありません。
強く押さえるのではなく、自然に支えることが大切です。
声帯閉鎖をトレーニングする上での注意点➁~息と声帯閉鎖のバランスを取ること~
声門閉鎖は「息の流れ」と一緒に成り立ちます。
息を完全に止めるのではなく、流しながら閉じる感覚を意識しましょう。
声帯閉鎖をトレーニングする上での注意点➂~少しずつ声帯筋を鍛えること~
声帯は繊細な組織です。過度な練習は声帯炎やポリープの原因にもなります。
裏声を出そうとしたとき、普段は出るのにうまく発声できない場合など、あると思います。
この時、声帯炎やポリープの可能性が大きいです。
練習を控え、声帯を休ませましょう。
よくある質問
声帯閉鎖に、息はたくさん必要?
A.適度な息が、声帯閉鎖には欠かせません。
声帯閉鎖には、空気圧の使い方がカギとなっていきます。
声帯より上側の空気圧を、「声門上圧」。
肺から送られてくる息の空気圧を、「声門下圧」と言います。
声帯閉鎖には、この「声門上圧」が高い状態を保つ必要があります。
声を出すとき声門下圧、すなわち吐く息が多いと、上手く声帯閉鎖させることができません。
声帯閉鎖を保つには、響きが損なわれないよう適度な息を使うことが必要です。
声帯閉鎖の練習は、喉を傷つける?
A.過度な練習は、声が出し辛くなる原因となります。
声帯閉鎖の練習は、声帯を強く振動させる物。
筋トレと同じで、過度な練習は声帯を疲弊させてしまい、閉鎖不全など疾患に繋がります。
歌の上達のためにも、適度な練習を心掛けていきましょう!
喉締めと声帯閉鎖の違いは何ですか?
A.喉周りの筋肉を過度に緊張させてしまうか、声帯を閉じるのかの違いです。
言葉のニュアンスから、混同されやすい「喉締め」と「声帯閉鎖」
実は、全く違います。
喉締めとは、声を出すために過度に筋肉を緊張させてしまい、声が出し辛くなってしまう状態。
声帯閉鎖は、声を出すために声帯を閉じる行為。
誤った声帯閉鎖の練習をしてしまうと、喉締めに繋がってしまう場合があります。
ぜひ切り分けて考え、喉締めになっているか、声帯閉鎖が上手くできているか、自身の状態を確認しながら練習していきましょう。

声帯閉鎖の感覚を掴んで、声の可能性を広げましょう!
声帯閉鎖は、歌声をコントロールするうえで欠かせない技術です。
声帯閉鎖は「声を閉じる」だけでなく、「声を自由に解放する」ための基盤です。
ゆっくり意識していけば、必ず声にとって良い作用をもたらします。
ぜひ、普段のトレーニングに取り入れてみてください!
声帯閉鎖を実践してみたい方はこちら!