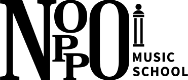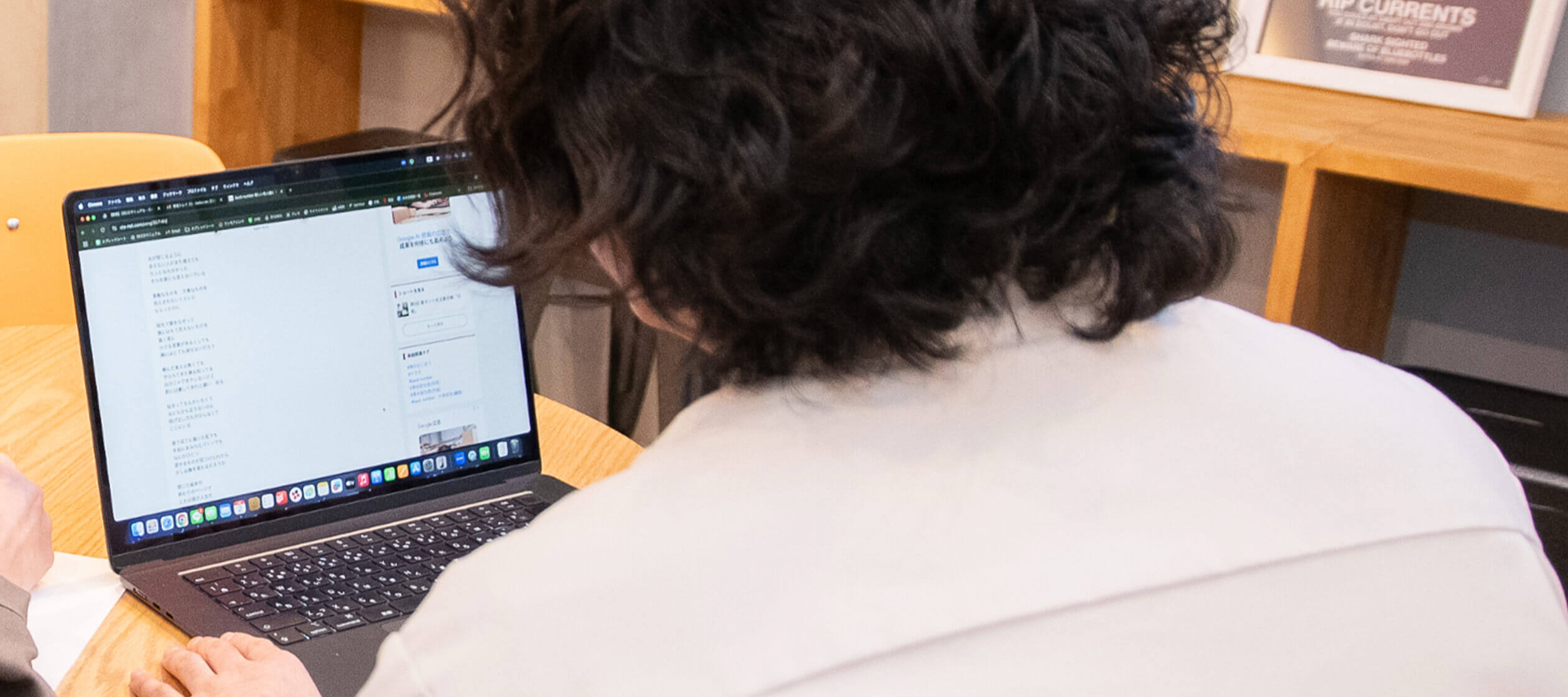歌声や話し声の魅力は「声帯そのものの音」だけで決まるわけではありません。
実際に耳に届く音は、声帯で生まれた振動が声道という空間を通り、共鳴・増幅されて形作られます。
なかでも重要な役割を果たすのが「鼻腔共鳴」です。
鼻腔共鳴は声に独特の明るさや柔らかさ、そして遠くまで届く響きを与えてくれます。
このコラムでは、鼻腔共鳴の仕組みからトレーニング方法、を詳しく解説します!

鼻腔共鳴とは?
「鼻腔共鳴」とは、声帯で発せられた音が頭部の前方、鼻の奥に広がる共鳴腔に響くことで得られる共鳴効果を指します。
人間の共鳴腔は大きく分けて以下の3つに分類されます。
• 咽頭腔:喉の奥、声帯から口や鼻に至るまでの空間
• 口腔:口の中の空間
• 鼻腔:鼻の奥に広がる空間
鼻腔は骨や粘膜に囲まれ、狭く複雑な形をしています。
このため、鼻腔に響く音は独特の「倍音」を生み出し、声を柔らかく、また遠くに飛ばしやすくしてくれるのです。
この部分を利用しながら発声することで、通常時より声を楽に響かせることができます!
鼻腔共鳴のメリット
1. 「倍音」によって、声の明るさを生む
鼻腔に響きが加わると、声に「キラリ」とした明るさが宿ります。
オペラ歌手やミュージカル俳優の声が遠くまで届くのは、この響きが大きく関係しています。
これは、声の「倍音」が変化するためです。
「倍音」とは、普段聞こえている音「基音」と同時に発生している音になります。
人の耳に届く音は、倍音を含んだ音になるので、単一の音だけが聞こえているという状況は実はほとんどないのです。
人の声に個性がそれぞれ生まれるのは、この倍音があるからです。
この時、倍音が協調された声は、通常時より響き、明るい声質に聞こえます。
歌唱においては、人は少し明るい音色を好む傾向があるので、鼻腔共鳴を使い、意識して音色を操作することが必要です、
2. 声の遠達性を高める
鼻腔共鳴は、いわば「音のスピーカー」の役割を果たします。
同じ音量で発声しても、鼻腔を適切に使えている人の声は、より遠くの人に届きやすいのです。
これも、「倍音」がより豊富になることで、通常時よりも人の耳に届きやすい声になります。
3. 声に柔らかさを与える
鼻腔共鳴が不足すると、声は平板で硬い印象になりがちです。
逆に適度に響かせると、声が柔らかく人当たりのよい音色になります。
高音時にも、声帯に負担をかけた硬い音色ではなく、柔らかい音色のまま発声することができます。
4. 話し方が変わる
「鼻腔共鳴」は歌唱だけでなく、日常会話やスピーチでも有効です。
声の柔らかさは、聴き手に対して心地よさと安定感を持たせることができます。
また、届きやすい声にもなるので、聞き返されることが少なくなります。
特に、アナウンサーやナレーターのような、何かを伝える職業の方の多くは、この「鼻腔共鳴」を利用しています。
自分の思いや考えを伝えるためにも、欠かせないテクニックの一つです。
5. 声の健康を保つ
鼻腔共鳴を意識することで、声帯への負担が減り、長時間歌っても疲れにくくなります。
これは、共鳴が声を効率的に増幅し、無理な力を使わなくても声が通るようになるからです。
プロの歌手が大きなステージで声を響かせ続けられるのも、鼻腔を含めた共鳴腔を最大限に活用しているからです。
鼻腔共鳴を実践したい方は「発声基礎コース」へ!鼻腔共鳴とミックスボイス
鼻腔共鳴は、ミックスボイスの習得に大きな影響を与えます。
ミックスボイスとは、裏声と地声の中間の声。
鼻腔に振動させる筋肉の動きは、声帯を引き上げ、ミックスボイスの状態に促しやすいと言われています。
鼻腔に振動させる筋肉の動きは、声帯を引き上げ、ミックスボイスの状態に促しやすいと言われています。
ただ、これだけだと、かなり裏声に近い状態になりやすいです。
ここで、口腔の意識も兼ねて発声していきます。
しっかりチェストボイス(地声)を響かせながら、ゆっくり鼻腔にも引き上げていく。
これで、芯のあるミックスボイスを出すことができます。
安定したミックスボイスには、鼻腔共鳴と口腔共鳴のバランスを取ることが大切です。
自身の声質にもよりますので、得意な部分からトライしてみましょう。
鼻腔共鳴で歌う歌手
鼻腔共鳴を利用して歌う歌手を、2名ご紹介します。
男性、女性、それぞれチェックしてみましょう!
RADWIMPS/野田洋二郎
中島美嘉
鼻腔共鳴のやり方
鼻腔共鳴は「鼻腔に響かせる」ことですが、単純に鼻から息を出すこととは異なります。
正確には、口腔と鼻腔をつなぐ「軟口蓋(なんこうがい)」の開閉具合が重要です。
口の中を観た時に、のどちんこ(口蓋垂)の周りに柔らかい筋肉があると思います。
これが、「軟口蓋」です。
軟口蓋は元々、嚥下(飲み込み)時に鼻に食べ物が入らないようにするための筋肉です。
この軟口蓋が吊り上がることで、口腔内も広がり共鳴腔としての役割が大きくなります。
そして、この軟口蓋は一度吊り上がった後少しだけ下がる動きを見せます。
このとき響きは一部分が伝わり、音は「副鼻腔」の方に広がります。
実は、一般的に言われている「鼻腔共鳴」とは、「副鼻腔共鳴」なのです。
もしくは、「鼻根」(眉間にある鼻の付け根部分)に響いているといわれています。
鼻腔共鳴と鼻声との違いは?
鼻腔共鳴と同時に比較されやすいこの言葉。
実は、全くの別物です。
鼻声は、「軟口蓋が下がり鼻から息が抜け、鼻腔を中心に声が共鳴している状態」です。
言葉のあやは本当に難しいですが、良く使われる鼻腔共鳴は実は「鼻腔」をそこまで利用していないのです。
実際に鼻腔を中心に発声してしまうと、「少しこもった、詰まったような声」に聞こえてしまう傾向があります。
また、ナ行やラ行などの滑舌も不明瞭になってしまいます。
いま鼻声になっているか、より良く共鳴できているか、しっかり判断しながら取り組んでみましょう。
鼻腔共鳴で歌ってみたい方は「ボーカルコース」へ!鼻腔共鳴の練習方法
鼻腔共鳴のコツを掴むためには、感覚をつかむ練習と筋肉のコントロールが欠かせません。
トレーニングを重ねて、鼻腔共鳴を実感していきましょう!
1. ハミング練習
もっとも基本的な方法がハミングです。
口角を少し上げ「んー」と口を閉じて声を出すと、自然と鼻腔に振動が伝わります。
このとき鼻の付け根や額のあたりに響きを感じられるかを確認します。
この時鼻から息が多く漏れ、声が掠れているとうまく鼻腔共鳴できていません。
しっかり、かつ楽に響く感覚を探してみましょう。
2. ハミングから母音へ
「んー」とハミングで響きを感じたら、そのまま口を開いて「あ」「い」「う」などの母音に移行します。
鼻腔の振動が残ったまま母音に変わるのが理想です。
音程はそのまま、また響が落ちないように注意しましょう。
3. 軟口蓋のコントロール練習
口角を少し上げながらあくびをするように喉を開けると、軟口蓋が自然に持ち上がります。
この状態で声を出すと、鼻に抜けずに響きだけが鼻腔に伝わります。
4. 高音域での鼻腔共鳴
高音になるほど鼻腔共鳴の助けが必要です。
ミドルから高音(E4~B4など)にかけては、意識的に「額に響かせる」イメージを持つとスムーズに出やすくなります。
低音でまず「ん―」とハミングで発声し、「あー」に切り替えます。
高い響きを保ったまま高いキーに繋げて出してみましょう。
普段より声を張らずに高いキーが出ると思います。
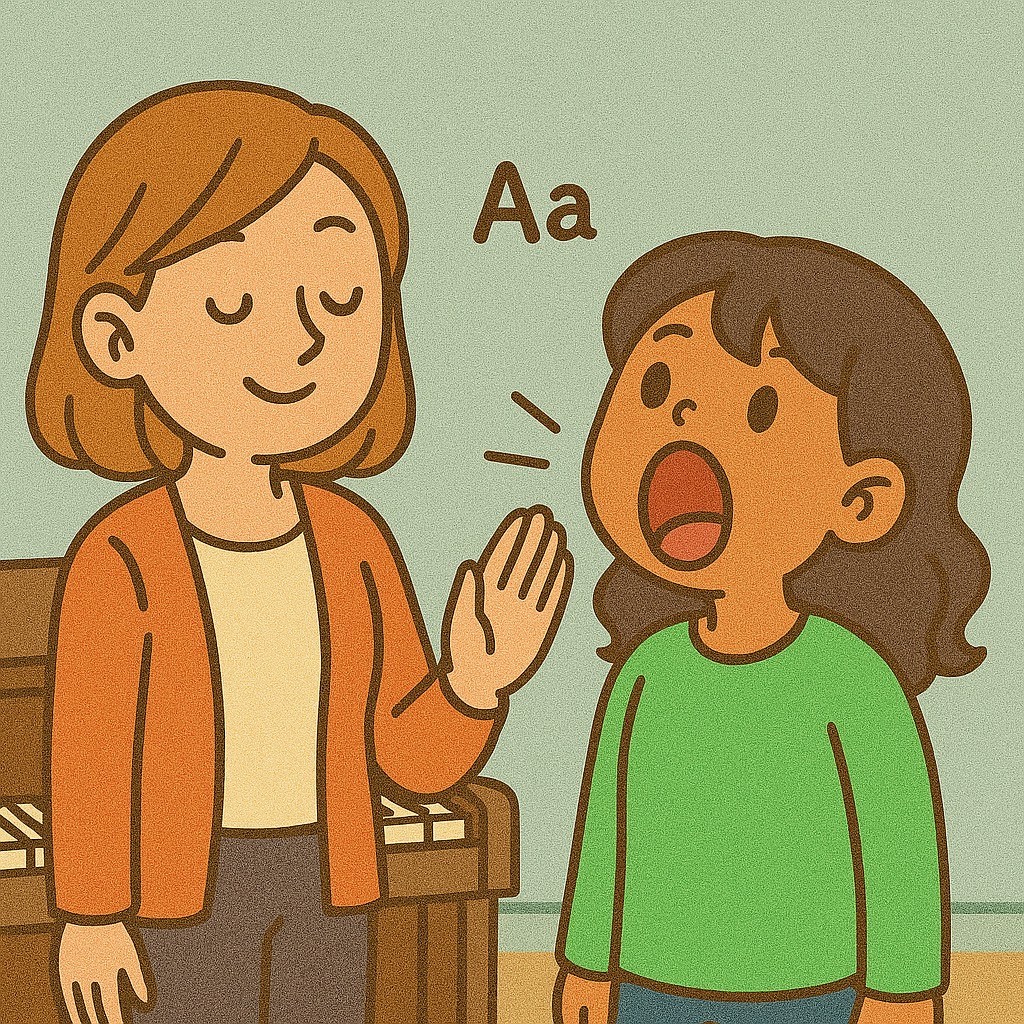
鼻腔共鳴を練習する上の注意点
1. 鼻腔共鳴しすぎない
鼻腔共鳴を意識しすぎると「鼻詰まり」のような声になってしまいます。
また、口腔の響きが使えず、薄っぺらい音になりやすいです。
あくまで声の彩りとして活用し、バランスを取っていくことが大切です。
2. 体全体を使いながら、鼻腔共鳴を意識する
共鳴は口や鼻だけではなく、胸や背中など身体全体が関わります。
正しい姿勢と呼吸が土台にあることを忘れてはいけません。
3. 録音で鼻腔共鳴ができているか、確認する
自分の耳で聴く声と他人が聴く声は違います。
練習の際には録音し、鼻声になっていないか確認しましょう。
鼻腔共鳴についてのよくある質問
Q1. 鼻腔共鳴を使うと必ず良い声になるのですか?
A. 鼻腔共鳴は声を魅力的にする要素の一つですが、それだけに頼ると声が細くなったり不自然になります。
口腔や咽頭の共鳴とバランスをとることが大切です。
Q2. 鼻腔共鳴を意識すると声が鼻に抜けてしまいます。
A. それは「軟口蓋」が下がりすぎている可能性があります。
あくびをするように軟口蓋を上げ、息は口から出しつつ響きだけを鼻腔に伝える感覚をつかみましょう。
Q3.鼻腔共鳴の実感が中々掴めない・・・!
A.声帯の振動が弱く、共鳴を実感できていないかもしれません。
声帯の振動は、響きの軸となります。
よって、声帯の振動がある程度ないと、鼻腔共鳴を実感することが難しい場合があります。
まずは、「ネイ」の練習で、声帯をしっかり閉じ、振動させることが必要です。
声量が出てきたら、鼻腔共鳴にもトライしてみましょう!

鼻腔共鳴で、新たな可能性を!
鼻腔共鳴は、声に明るさ・柔らかさ・遠達性を与える重要な要素です。
ハミング練習や軟口蓋のコントロールを通じて感覚をつかみ、口腔や咽頭とのバランスを整えることで、より魅力的で伸びやかな声を手に入れることができます。
歌唱やスピーチにおいて「よく通る声」「聞き取りやすい声」を目指す人にとって、鼻腔共鳴は欠かせない技術です。
ぜひ日々の練習に取り入れて、あなた自身の声の可能性をさらに広げてみてください。
良い歌ライフを!
第一歩を踏み出しましょう!「ボイトレ初心者コース」へ!