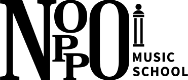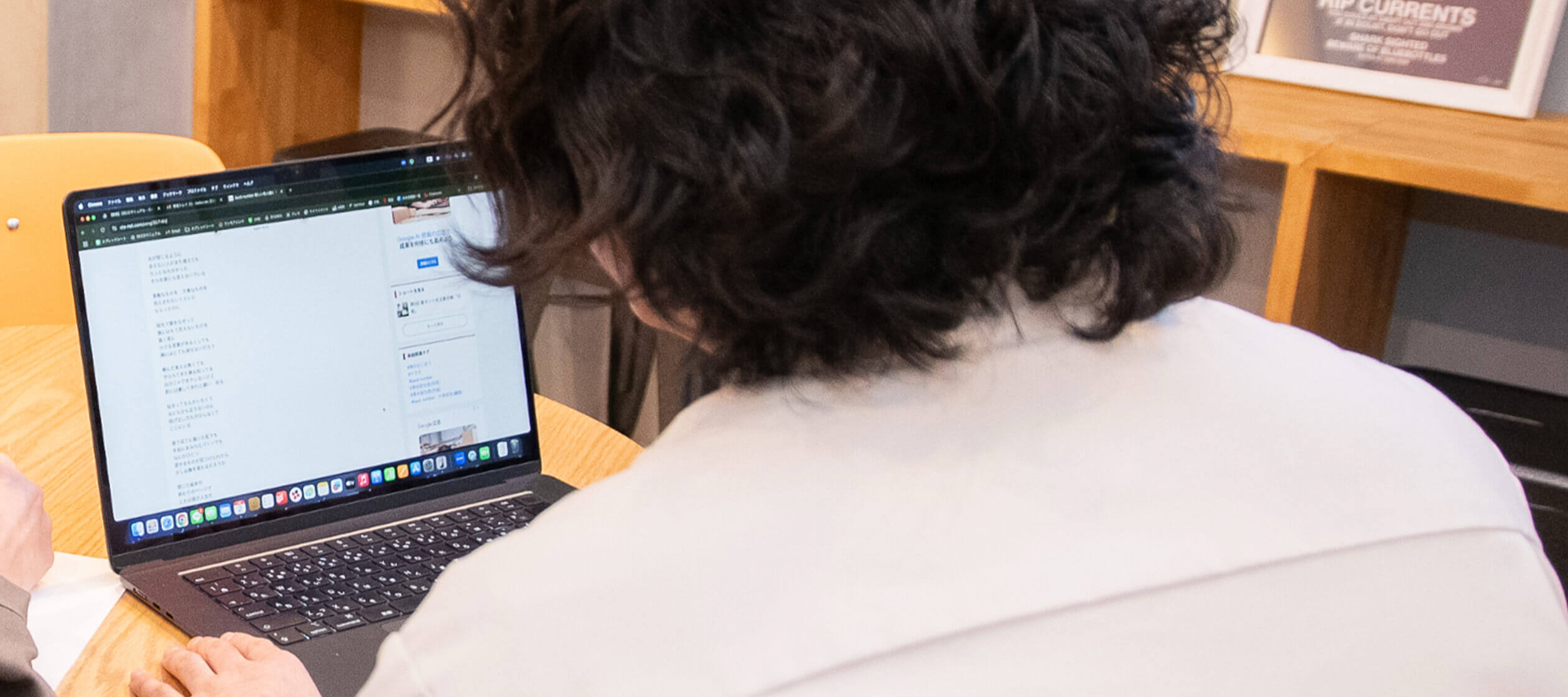歌を練習していると、「こぶし」という言葉を耳にすることはありませんか?
演歌、歌謡曲、カラオケ採点など、様々な場面にて聞く機会があると思います。
特に身近なものでは、カラオケ採点にて「こぶし」という項目があり、加点UPのコツとして紹介されています。
歌唱のなかでこぶしをいれると、より彩りのある表現となり、聴き手を楽しませることができます。
ただ、
「こぶしって、どうやって歌の中に入れるの?」
「そもそもこぶしって何?」
「手の動きとは関係あるの?」
など、疑問に思う方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、謎多き「こぶし」について、こぶしの正体・使い方・練習法、そしてその魅力を徹底解説致します。
このコラムで、いつもの歌をよりレベルアップしていきましょう!

歌の「こぶし」とは?
こぶしとは、「一つの音の中で、音程を上下に装飾的に揺らす歌唱法」です。
元のメロディーが細かく変化させられた音程を、「装飾音符」と言います。
これは、元の音程そのものが変化するのではなく、細かな音程の後、元の音に戻る場合を指します。
クラシックでは、「メリスマ」や「トリル」、「ターン」などの用語が挙げられます。
※ターンやトリルはそれぞれ装飾される音が決まっていますが、メリスマは多種にわたる音程変化を指します。
POPSでは、「フェイク」というように表現されることが多いです。
「こぶし」も、これら装飾音符の一員となります。
「こぶし」の歌い方
「具体的には、「音を上に持ち上げてから元に戻す、または下げて戻す動きを瞬時に行うこと」です。
例:「あ〜なた〜」の「な」の部分を「なぁ↑なぁ↓」と動かすようなニュアンス。
よくビブラートと混同されることが多いですが、具体的には「ビブラートの1部分のみ」を利用したものと考えられています。
演奏効果としては、フレーズに変化を持たせることで、シンプルになりやすいメロディーを、より感情豊かに、また哀愁を交えて表現することができます。
特に、演歌などではそれぞれのフレーズの最後に使用されることが多いとされています。
大宮のボイトレスクール「NOPPO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!こぶしを使っている歌手・楽曲
ここでは、こぶしが使用される楽曲について解説します。
聞き比べながら、何がこぶしかを掴んでいきましょう。
「^」のついている箇所が、こぶしの箇所になります。
➀北酒場/細川たかし
例:「きた~の^~ さかばどうりには^~」
➁ハナミズキ/一青窈
例:「そ~らを~ おしあ^~げて~
てをの^~ばす^~きみ~ ごが~つの~ こと~」
➂糸/中島みゆき
例:「よ~このいと~は~わ~たし^~」 ※サビ2フレーズ目
比較的、演歌や歌謡曲、またバラードのテンポの楽曲にて使用されることが多いです。
皆さんが好きな楽曲にも、こぶしが隠されているかもしれません!
ぜひ、探してみましょう!
歌の「こぶし」の意味・語源
実はこぶしは、「拳」ではありません。
演歌歌手が歌っている時に拳を上げる動きをするため、混同する人も多いかと思います。
演歌が流行し始めた1960年代から、より多く使用されてきたと言われています。
実は、こぶしの語源は、「小節」を訓読みした「こぶし」なのです。
楽譜などに記載されない装飾的な発声、またそれによる細かい節回しを指します。
起源は、古くから伝わる民謡からその節は歌い継がれてきており、それが現代の演歌やPOPSにも使用されているのです。
歌のこぶしの仕組み
こぶしは、短い音程変化の組み合わせとされています。
歌の「こぶし」における音程の変化
基本的に2種類あり、
「音程が上行し、元の音に戻る」例:ド↗レ↘ド
「音程が下行し、元の音に戻る」例:ド↘シ↗ド
この音程の変化を高速に行う。
使い分け自体に傾向や規則性はありませんが、どちらのこぶしが得意かは人により別れる部分があるかと思われます。
まずフレーズの最後に使用し、どちらが自分の歌いまわしに合うか試してみましょう。
歌の「こぶし」による声帯・周辺筋肉の動き
こぶしをかけるとき、声を出すための器官である「声帯」は以下の動きをしています。
今回は、上行形「ド↗レ↘ド」のこぶしの場合についてお伝えします。
1. 軽いピッチ上昇:輪状甲状筋(声帯を引き伸ばし薄くする筋肉)が軽く収縮
2. 戻す動き:甲状披裂筋(声帯が閉じる力を調節する筋肉)が優位になり、音程を下げる
3. 息の流れと共鳴の調整:息の量を一定に保ちながら喉頭の高さと共鳴腔を微調整
これらは瞬間的に行われるため、筋肉の協調性、脱力が出来ており、十分に伸縮できる事が必要です。
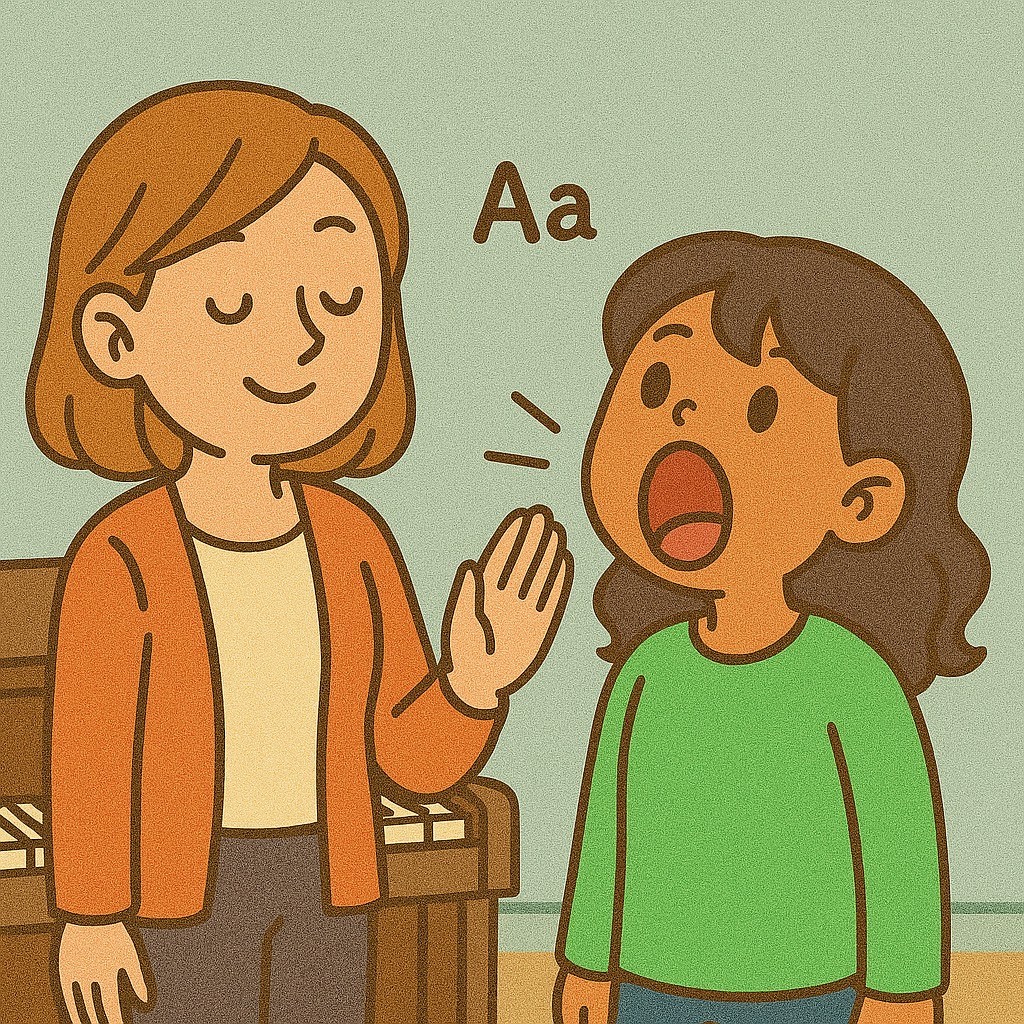
歌の「こぶし」と、「ビブラート」の違い
「こぶし」と「ビブラート」は混同して考えられやすいです。
ここでは、それぞれの違いについて解説致します。
こぶし
音程変化:瞬時の上下
持続時間:短い
感情表現:哀愁・情熱
使用箇所:語尾や感情の山
ビブラート
音程変化:一定周期の揺れ
持続時間:長く持続
感情表現:温かみ・伸びやかさ
使用箇所:ロングトーン全般
こぶしは装飾的、ビブラートは持続的という違いがあります。
両方を使い分けることで、歌の表情は格段に豊かになります。
大宮のボイトレスクール「NOPPO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!歌の中で「こぶし」を入れるタイミングと効果
ここでは、こぶしを入れる効果について解説します。
こぶしも、付きすぎてしまっては効果が発揮できません。
しっかり見極めながら歌唱しましょう。
歌の中で「こぶし」を入れるタイミングと効果 その1~感情を強調する~
• 切なさを表すバラード
• 民謡や演歌での情念表現
歌の中で「こぶし」を入れるタイミングと効果 その2~メロディのアクセントとして~
• サビの入り口やフレーズ終わり
• 単調なメロディに動きを与える
歌の中で「こぶし」を入れるタイミングと効果 その3~聴き手を引き込むニュアンス~
• 「泣き」の表現
• 言葉の情感を増幅
歌の中で「こぶし」を入れるタイミングと効果 番外編~こんな時には使わないほうがいい!~
・アップテンポで、言葉が詰まっているフレーズ
・音程の変化がすでに激しい

歌の「こぶし」トレーニング!歌を華やかに!
歌の「こぶし」トレーニング ステップ1:音程装飾の感覚を身につける
1. 鍵盤で同じ音を弾き、その半音上を素早く行き来します。
2. 「あー↑あー↓」と上げ下げを意識。
歌の「こぶし」トレーニング ステップ2:母音ごとに練習
• 「あ」「え」「お」は開口母音のため、音程の操作がしやすく、比較的こぶしがかけやすいです。
まず自分の得意な母音にて練習してみましょう。
• 「い」「う」は口腔内が狭くなりやすく、難易度が上がります。
「え」や「お」に口の形を利用し、力みがないように挑戦してみましょう。
歌の「こぶし」トレーニング ステップ3:短いフレーズに組み込む
音程の操作に慣れてきたら、シンプルなメロディーの楽曲で変化させていきます。
• 例:かえるの歌「かえ〜る〜」の「え」の部分で装飾
歌の「こぶし」トレーニング ステップ4:曲に応用
• 好きな演歌やバラードを参考にしながら、歌唱に取り入れる
• 最初はオーバーに入れて、徐々に自然にしていく
歌の「こぶし」トレーニング ステップ5:声帯周辺の筋肉トレーニング
発声する上での筋肉の動きを改善することで、よりこぶしは付けやすくなります。
声帯周辺の筋肉トレーニング➀ ハミング練習
• 鼻腔共鳴を使いながら軽く上下のピッチを揺らす
声帯周辺の筋肉トレーニング➁ リップロール
• 口を閉じて唇をブルブル震わせながらピッチ変化を入れる
声帯周辺の筋肉トレーニング➂ 喉のリラックス
• ストレッチや深呼吸で喉頭を上下させる練習
• 舌の奥を緩めることで滑らかなこぶしが可能になります。
こぶしだけでなく、発声そのものの改善にもつながります!
歌のこぶしにまつわる、よくある質問
Q. どうしても、力みが生じてしまう。
A. 息の流れを止めてしまっているかもしれません。
息を止めてしまうと音程の変化がつきにくくなります。
あくびや腹式呼吸などで、息の流れをキープしながら行いましょう。
Q. カラオケで、ビブラートと判定されてしまう・・・!
A. こぶしを長くしすぎています。
音程の変化が長くなり、ビブラートに寄りすぎるとこぶしの特徴が薄れてしまいます。
装飾の一瞬感を意識し、効果的に演奏するよう心掛けましょう。
Q.こぶしは絶対使わないといけない?
A.使い分けられればOKです!
こぶしは、フレーズの中で適宜使うことができると、効果的です。
必ず歌の中でこぶしをしなければならないということはありません!
アーティストの歌唱を聴き、こぶしの活かし方を研究してみましょう!

こぶしで、より彩りのある歌唱を!
こぶしは単なる演歌の技法ではなく、音楽的な「泣き」と「情」を表現する日本独自の装飾音です。
適切な場所で自然に入れられれば、歌の説得力が増し、聴く人の心を強く揺さぶります。
ぜひ、歌唱に取り入れてみてください。
良い歌ライフを!
大宮のボイトレスクール「NOPPO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!