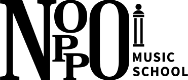こんにちは!
NOPPO MUSIC SCHOOL ミュージカル講師の花音美燈です♪
今回は、ミュージカルのお稽古がどのように進められるかを簡単にご紹介したいと思います。
現場によって細かい部分は異なりますが、概ねこのような流れで行われるのではないかと思いますので、初めてのお稽古を前にドキドキしている方、ぜひ参考にしてみてくださいね!
あくまで例ですので、現場によって少しずつ異なる場合もあります。
呼び方も少し異なる場合がありますが、前知識として「こういうお稽古が存在するんだな」と知っておくことで、急に現場に入っても慌てずに済みますよ♪
では早速、順を追ってご紹介します!
(1) 顔合わせ、読み合わせ
最初に「顔合わせ」をして、お稽古期間がスタートします。
顔合わせとは、公演に関わる出演者・スタッフが初めて一堂に会し、挨拶をする場です。
(照明さん、音響さんなど現場スタッフの方はこの時点でいらっしゃらないことが多いので、実際に関係者全員が集うのは劇場入り後となることが多いです。)
内容は現場によって様々ですが、演出家の挨拶から始まり、スタッフ紹介、そして出演者が一人一言ずつ挨拶していく……というパターンが多いでしょうか。
その後、制作より稽古スケジュール等事務的なお話を共有し、少しお稽古に入ったり、親睦会があったり……と、その後の時間の使い方は本当に様々です。
歌だけではなく台詞も多めのミュージカルですと、顔合わせ後にそのまま「読み合わせ」をすることがあります。
読み合わせとは、立たずに座ったまま、みんなで台本を読んでいくことを言います。
読み合わせのやり方はいくつか種類があるので詳細は割愛しますが、とにかく、一度みんなで頭から終わりまで台詞を合わせることで、全体像を掴みます。
(2) 歌稽古
ミュージカルのお稽古では大体「歌稽古」から始めていきます。
ストレートプレイだとすぐに立ち稽古に入ることが多いので、このお稽古スタイルはミュージカル特有のものだと思います。
台詞のほとんどないポップ・オペラですと、顔合わせのあと早速歌稽古に入ることもあります。
歌稽古は、歌うことに特化したお稽古です。
主に歌唱指導の方が前に立ち、お稽古をしていきます。
一人ずつゆっくり音取りをしている時間はないので、譜面を読む力を付けておくか、一度聞いただけで音を取れるか、どちらかの能力がないと四苦八苦するかもしれません。
また歌稽古の際には、録音できるものを持ってきて、あとで復習できるようにしておくことをおススメします(スマートフォンでもOKですが、権利の都合上、個人での録音NGの場合もありますので、必ず確認してから録音するようにしてください)。
もし先に譜面や音源をもらっているのであれば、事前にさらってから稽古に臨むのが賢明です。
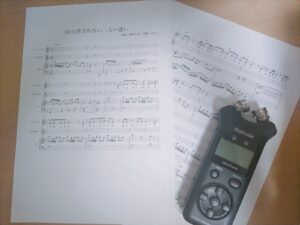
作品が完成に近づいてくると、音楽監督がいらしゃって、よりコアな部分の指導を受ける時間も設けられます。
(3) 振り付け
ダンスが多いミュージカルですと、歌稽古の後に「振り付け」が行われます。
ダンス稽古は歌が歌える前提で進みますが、歌稽古の翌日に振り付けということもあり得ます。
一度稽古したものは「出来るもの」とみなされますので、できなかったところや覚えていない部分は、聞くなり自主練するなりして、即座に対応することが求められます。
(4) ステージング
音楽部分のパーツが整ったら、「ステージング」に入ります。
場合によってはステージングと振り付けが同時進行のこともあります。
ステージングとは、「ミザンス」を付けていくことです。
つまり、「このシーンでは誰々が上手から出てセンターまで来て台詞を言う」「このタイミングで誰々が下手に走ってハケる」等の動きをつけていきます。
どの程度の指示があるかは演出家や作品によっても異なりますが、パッケージの決まっている有名作品では、かなり細かく立ち位置が設定されている可能性が高いです。
慣れないうちは覚えるのが大変かもしれませんが、適宜メモを取りながら間違いの無いよう覚える必要があります。
大人数が出るシーンだと、一人場所を間違えるだけで事故が起きる可能性があります。
場所だけでなく導線(誰の前・後ろを通る等)も一緒に覚えます。
なお、台本を見ている余裕は無いので(邪魔になることもあります)、この時点で台詞もある程度覚えているべきです。
お稽古は大体「何幕何場〜何場」という括りか、「M◯」という括りでスケジュールが出ます。
「M」というのは「ミュージックナンバー」を差すもので、基本的には冒頭の曲から順に「M1,M2,M3…」と振られています。
そのため一気に台本を丸ごと覚えなくても、スケジュールに合わせて順に覚えていけば大丈夫です。
(とはいえ、時折急にスケジュール変更されることもありますが……(汗))
(5) 返し稽古
最後までステージングが終わったら、頭から「返し稽古」をしていきます。
返し稽古ではより芝居の深い部分を指示されたり、変更点があったりと、より作品の質を高めるためにシーンを固めていきます。
とはいえ、場合によってはほとんど出来ないこともあります。
ゆっくり返し稽古する時間がない場合は、すぐに次の「通し稽古」に入ります。
(6) 通し稽古
細かい部分が仕上がったら、本番と同じように頭から終わりまで止めずに通す、「通し稽古」の段階に入ります。
可能な限り何度も通し稽古をすることで、本番の完成度を高めます。
通した後にフィードバック、それに応じて「抜き稽古」を行うこともあります。
粗をどんどん無くしていき、最高の状態で本番を迎えるべく、最終調整をしていきます。
普段使っている稽古場が本番のステージよりも狭い場合は、大きな稽古場に移って「実寸稽古」を行うこともあります。
実寸稽古を本番の舞台上でやれることもありますが、団体所有の劇場でない限り稀です。
(7) 衣裳付き通し
最後は衣裳をつけた状態で通し稽古を行う「衣裳付き通し」を行います。
衣裳を着た時の不具合はないか?早替えは問題ないか?等々もここで最終確認します。
ミュージカルでは一人で何役も演じることが多いので、早替えは付きものです。
どっちの袖でどれくらいの速さで着替えなければいけないか?きちんと整理した上で通し稽古に臨みましょう。
(8) 場当たり
劇場入りして最初に行う稽古は「場当たり」です。
音響さん、照明さん、舞台部スタッフさんとの合わせを中心に、ポジション確認等を実際の舞台上で行っていきます。
もちろん各シーンにおけるキャストのポジションも確認していきますが、スタッフさんと初めて合わせる時間なので、どちらかと言えばスタッフさんのための時間だと私は思っています。
時間がない現場だと、それこそ明かり合わせ・音合わせの確認で終わってしまうことも……。
本番で事故がないようにする為に、危険が伴う箇所も場当たりで確認していきます。転換、暗転確認などがよくある例です。
概ね場当たりでは「場当たり進行表」というものが作られているので、それに沿って進みます。
全体がブロックでいくつかに区切られているので、ブロック単位で進行します。
進み方としては、1ブロックの中の確認ポイントを順に押さえていき、確認ができたらそのブロック通します。
ブロック内で着替えがある際は、その通す時に着替えます。
確認している段階ではまだ着替えてはいけません。
いずれにしても演出助手より指示があると思うので、それ従って着替えたり着替えなかったりします。
(9) ゲネプロ
場当たりが終わったら、仕上げに「ゲネプロ」を行います。
「ゲネ」「GP(ゲーペー)」と略されることが多いですが、「ゲネプロ」もすでに略語で、正しくは「ゲネラルプローベ(Generalprobe)」というドイツ語です。
すべて本番さながらに通します。
一般のお客様がいない他は、本番とまるで同じです。
ただし関係者やプレスを招待している場合もあるので、客席で観ている方がいる可能性もありますし、カメラが入っていることも多いです。
(10) 本番
色々なことが目まぐるしく起きましたが、あっという間に本番です!

いかがでしたか?
一言で「稽古」と言っても、様々なことを行っているのがわかりましたでしょうか?
参考になれば嬉しいです♪
大宮のボイトレスクール「NOPPO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!