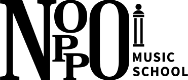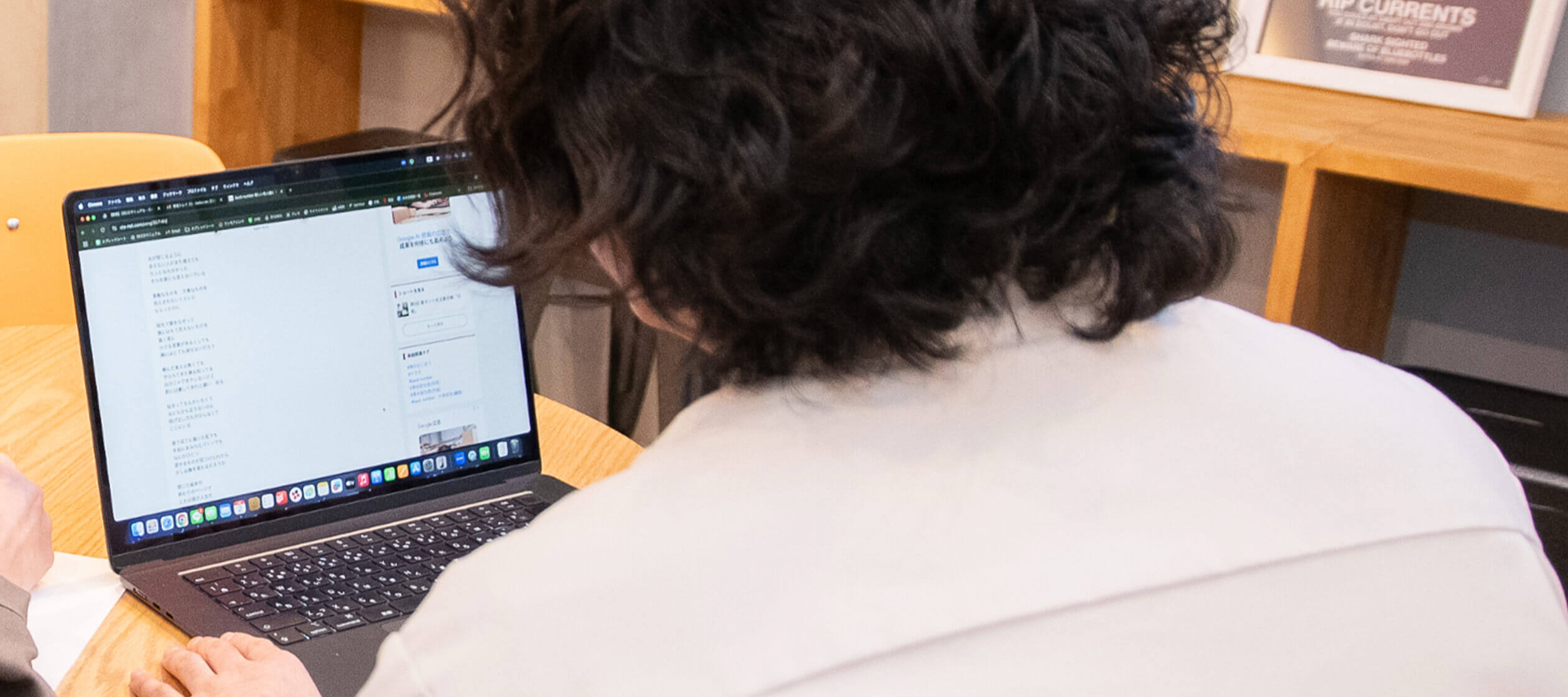はじめまして!
NOPPO MUSIC SCHOOLです!
「ビブラート」
歌を勉強していたり、カラオケで採点すると必ず出てくるこの言葉。
ビブラートのある歌唱は、とてものびやかに聞こえたり、迫力があったりととても評価されやすいです。
しかし、
「ビブラートって、どうやるの?」
「そもそもビブラートって何?」
と、疑問に思う方も多いと思います。
そこで今回は、
よく聞くけど、実態がいまいち分からない、
「ビブラート」について、やり方や練習方法していきます!
これを読んで、歌う時の楽しみ方の一つになれれば、幸いです。
では、参りましょう!
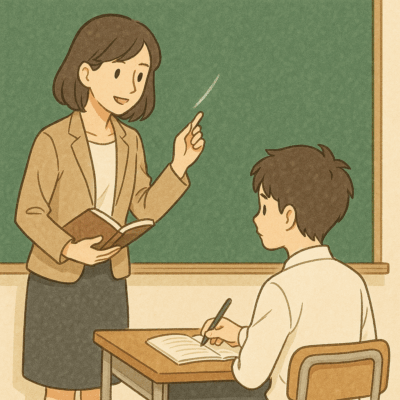
ビブラートとは?
ビブラートは、
「演奏・歌唱時において同じ音を保つとき、その音を揺らす演奏方法」
とされています。
オペラやミュージカルの歌唱だと、ロングトーンを伸ばす際、音が揺れているように聞こえると思います。
あの揺れが、「ビブラート」です。
では実際、音はどうなっているのか。
実はビブラートとは、「微細な音程の変化」なのです。
音は、基本的に空気が振動することで鼓膜に届き、聞こえています。
この振動が一定時間何回振動するかを表したのが、「周波数」です。
だいたいよく言われるのが、男性にとって高いラの音だと、440Hzと言われています。
音はそのままだと直接振動を感じることは出来ず、真っすぐとした音に聞こえますが、
この揺れが、
「5Hz~7Hz」程度動くと、ビブラートとして揺れて聞こえるのです。
これが、「ビブラート」の正体になります。
大宮のボイトレスクール「NOPPO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!ビブラートの効果とは?上手に使うメリットと注意点
ビブラートの1番のメリットとしては、
声がのびやかに聞こえることにあります。
短音でまっすぐ伸ばすよりも、微細に安定しながら揺れることで、音にうねりをもたらし、耳にとって聞きやすい音に。
クラシックの声楽などのマイクを通さない歌唱では、よりホールや室内の反響を促すことが出来るので、響く声として認識されます。
カラオケの採点においては、ビブラートも加点対称となるので、得点アップに繋がります!
ただ、過度に揺らすビブラートは時としてノイズと判断され、あまり聞こえが良くないものとされる可能性もあるので、注意が必要です。
録音して自分のビブラートを聞きながら、揺れるスピードや大きさを調節し、より良いビブラートを探してみてください!

ビブラートのやり方
ここまでビブラートについて少しマニアックな話も交えてお伝えしましたが・・・
どうすればビブラートがかけられるようになるのか。
「では、同じ音を伸ばして5Hzから7Hz揺らしてください」
と言われても、そんな事なかなかできません。
人間技じゃないです。
ビブラートを感覚的につかむためには、「声を出す器官を、適切に揺らす」ことが必要です。
声は、体の様々な筋肉や器官を利用して音になっています。
声を操作するうえで、自在にアプローチするためには、声を出すための器官の仕組みと、その使い方を理解しておく必要があります。
今回、ビブラートを出す上で重要な器官が、
・横隔膜
・声帯
・あごや口
この3つになります。
せっかくなので、1つずつ見ていきましょう。
ビブラートのやり方➀~横隔膜を使う~」
横隔膜とは、「呼吸をする際、肺を稼働させる筋肉」になります。
肺は自ら動くことは出来ず、「胸筋」と「横隔膜」を動かすことで稼働し、呼吸を行っています。
横隔膜は、腹部の筋肉を動かすことで使うことが出来ます。
これを、「腹式呼吸」と言います。
声は、息が「声帯」を通過することで振動し、音になります。
すなわち声の大本は、息になるわけです。
ですから、音の高低や大きさは、横隔膜の使い方によって変化していきます。
この横隔膜を使い、息をコントロールすることで音程を微妙に変化させ、ビブラートを作ることが出来ます。
ビブラートのやり方➁~声帯を上手く使う~
声帯とは、「声を出すための器官」です。
これがないとまず声は音になりません。
声帯は2枚のひだのようになっており、それらは声を出そうとするとこすり合いように動きます。
その間に息が通ることで、空気が振動し、音になります。
音の音高や大きさは、声帯の使い方によっても変化することが出来ます。
これを利用して、真っすぐ音を出す際に声帯を微細に変化させることで、ビブラートを出すことが出来ます。
ビブラートのやり方➂~あごや口を使う~
最後は、あごや口です。
あごや口は、声を出す際の最後に使う器官になり、声において基本的には、音量や言葉を司る器官になります。
口の形やあごの開き方によっても音は変化するので、微細に揺らすと直接的にビブラートがかかる感覚になると思います。
しかし、顎や口が変化してしまうと「力み」に繋がりやすくなり、正しい発声が難しくなる場合が多いので、テクニックとしてあまりおすすめされておりません。
ポップスなど細かい表現が必要な場合は、利用している歌手も多いので、横隔膜や声帯の使い方とは切り分けて考えていただけると良いと思います。

ビブラートができない理由と改善のヒント
ビブラートの仕組みややり方を解説しましたが
「分かっていても、できない!」
という方もいらっしゃると思います。
これは、歌う際に「体を過度に緊張させてしまっている」可能性があります。
歌う時、無理に声を出そうとして身体や喉周りの筋肉が過度に緊張し、十分に声が出ていない状態です。
ビブラートは、声を操作する器官を十分に使ったうえで行うので、
この状態のままだと、中々音にすることは難しいです。
少し揺れたとしても、力みの中の不安定さから起こる揺れの可能性もあるので、あまり良いビブラートとは言えません。
なので、「ビブラートが中々できない!」と感じた時には、腹式呼吸や発声練習で、楽な状態で歌う事からアプローチしてみてください。
自然と、ビブラートの糸口が見えてくることと思います!
大宮のボイトレスクール「NOPPO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!ビブラートでカラオケ高得点を採るコツ
カラオケの採点機能では、ビブラートは欠かせない機能です。
特に、あえてビブラートと認識させることが出来ると、より加点に繋がります。
カラオケでビブラートを使い高得点を採るコツは、ずばり「使いどころと長さ、細かさを意識する」しかし、カラオケ採点におけるビブラートの難しいところは、
「ビブラート」と「不安定さ」が両立しやすいところ。
勿論慣れている方では問題ありませんが、
不慣れなうちにビブラートを実践しようとすると、それまで保っていた安定性が下がりやすい傾向があります。
カラオケ採点の多くは、はっきりとしたビブラートが求められます。
細かすぎるビブラートや一瞬しかかからないと、不安定さとして判定されてしまい減点されてしまいます。
また、ロングトーンとも両立する必要があり、すべてのフレーズにビブラートがかかってしまうと、ロングトーンの項目が低い点数となってしまいます。
必ずそれぞれフレーズの中で、1秒以上ビブラートとロングトーンのフレーズを作りましょう。
また、細かすぎたり揺れが不安定なビブラートも、あまり高得点には繋がりません。
揺れを調節して、聴きやすく安定したビブラートを目指しましょう!
採点バーの表示を細かく見たり、採点結果のビブラートの項目をチェックして、より加点されやすい、減点されにくいビブラートを調節してみてください!
慣れてくると、自然と得点UPに繋がります!
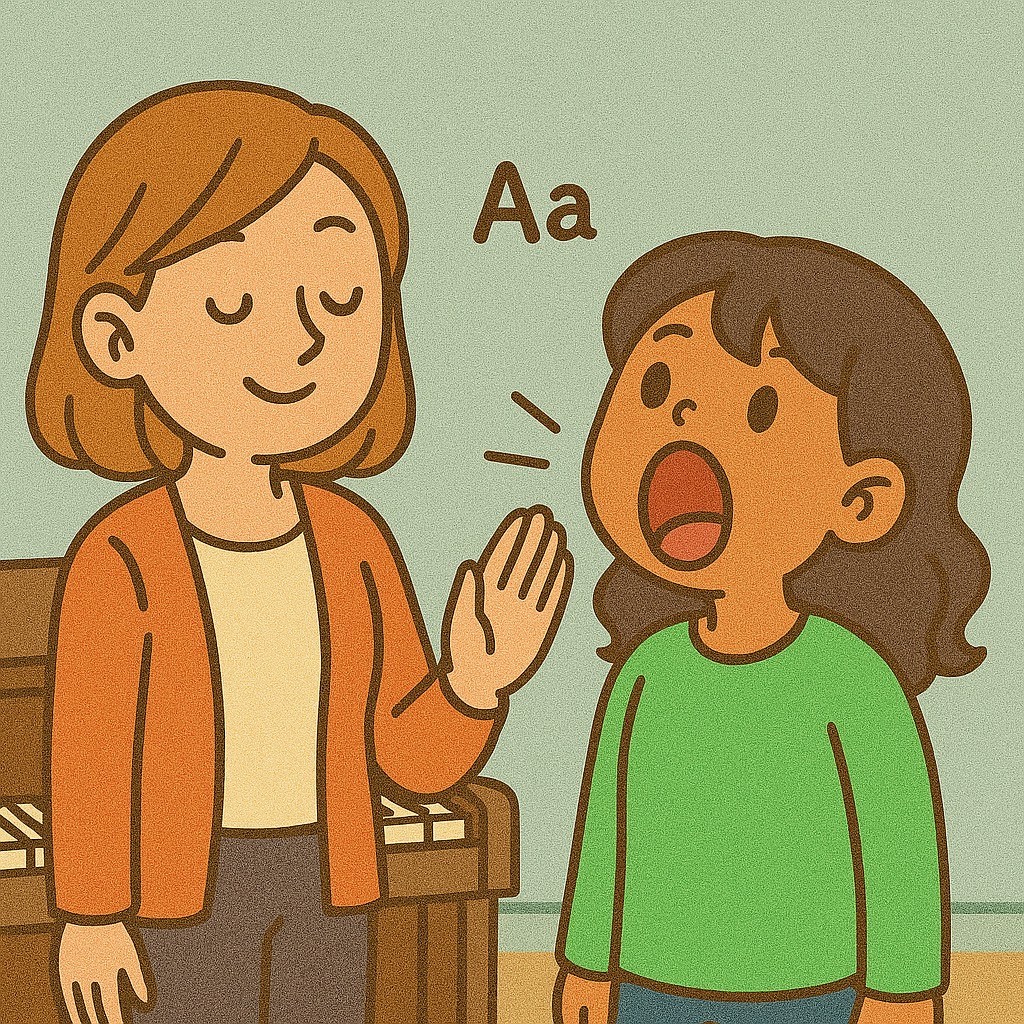
ビブラートの練習方法!自宅でできる簡単トレーニング
ここからは、ビブラートの具体的なトレーニング方法について解説します。
一人でも手軽にできる練習なので、ぜひやってみてください!
ビブラートの練習方法~音を上下させる練習~
➀自分にとって楽なキーで、「お」の母音で音を伸ばす。
※男性ならmid1C(低いド)、女性ならmid2A(低いラ)
➁ 出している音より1音高い音と、音程を2回上下させる。
※ドレドレド・・・のように
➂ 上記を、半音ずつ挙げながら繰り返す。
➃ だんだん、上下させるスピードを速くしていく。
以上です!
まずこの練習で、音を変化させることを体に覚えさせてください。
だんだん、単音を揺らすことが実感としてわいてくるお思います。
コツとしては、横隔膜や声帯を意識して稼働させることです。
無理に揺らさず、リラックスしながら行うとより効果的です!
最初は中々難しいと思いますが、ゆっくり音にしていきましょう!
是非やってみてください!
ビブラートに関するよくある質問
Q.自然とビブラートかかかってしまい、上手くコントロールできません・・・。
A.発声の不安定さが原因かもしれません。
呼吸や声帯の使い方が不安定だと、フレーズに意図せず「揺れ」が生じてしまいます。
まずは、腹式呼吸や発声のトレーニングで、声を安定させるところから始めてみましょう。
段々、真っすぐなフレーズを扱えるようになります!
歌の中で使い分けられるようになったら、ビブラートを体得した証拠です!
Q.ビブラートがわざと揺らしているように聞こえてしまうのはなぜ?
A.自然なビブラートができていない可能性があります。
力みによってビブラートをかけてしまうと、不自然な揺れになってしまいます。
不自然な揺れは、カラオケでも減点対象です。
まずは脱力し、自然とビブラートがかかる感覚を身に付けていきましょう!
Q.ビブラートは細かいほど良い?
A.ゆっくりなビブラートと使い分けられると効果的です。
細かいビブラートは、速いテンポの曲などには合いますが、
バラードのようなゆったりしたテンポの曲には、緩やかなビブラートが適しています。
両方意識して扱えるよう、ビブラートを練習していきましょう!

ビブラートを身につけて、歌に表現力を!
今回は、ビブラートについて解説いたしました!
ビブラートが身につくことで、よりバリエーション豊かな表現となります!是非、楽曲にも応用し、楽しみながら練習してみてください!
良い歌ライフを!
大宮のボイトレスクール「NOPPO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!