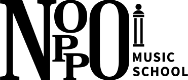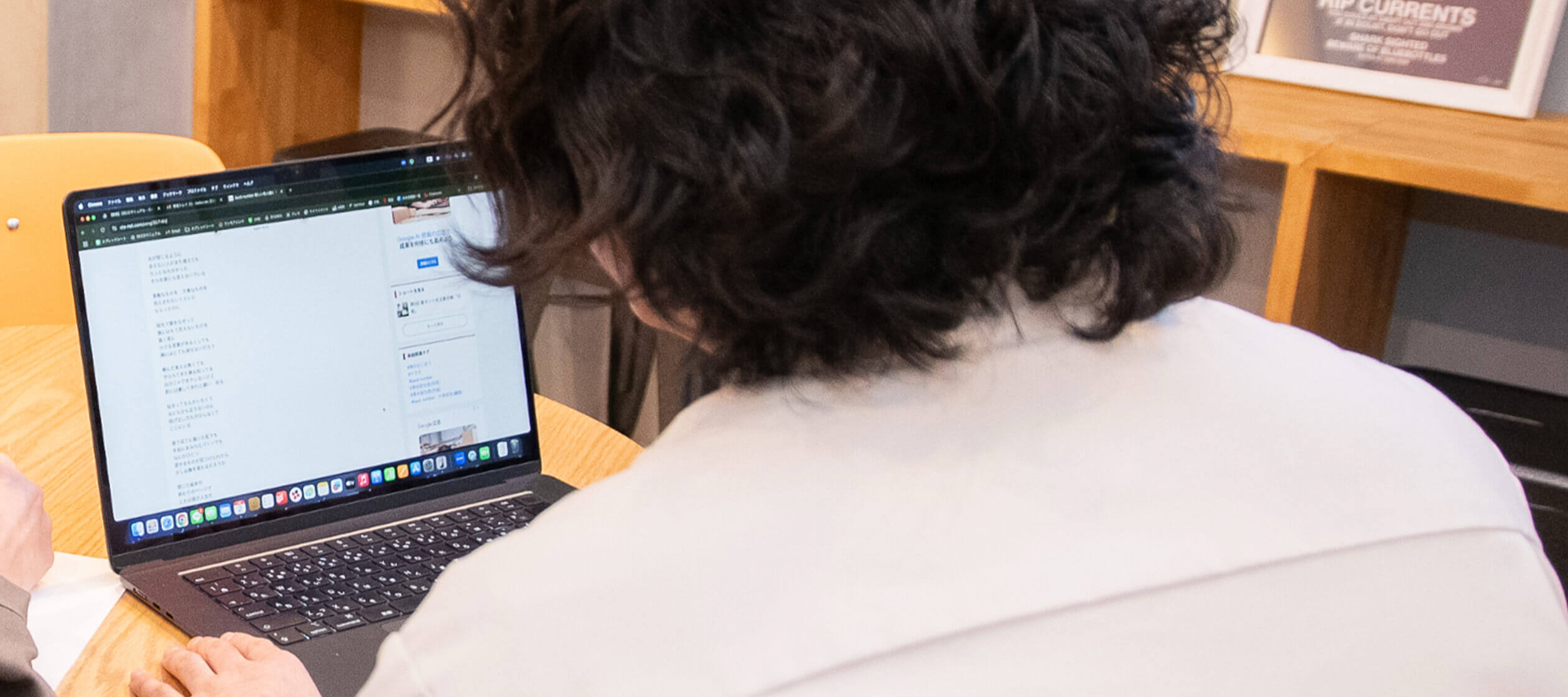独自の音楽性と文学的な歌詞で多くのファンを魅了するサカナクション。
彼らの楽曲は一見シンプルなサウンドに聴こえても、その裏側には巧妙なフレーズ設計や息づかいが潜んでいます。
本記事では、そんなサカナクションの歌い方に焦点を当て、楽曲分析から実践的な歌い方までを段階的に解説していきます。
『怪獣』のパフォーマンスに見る歌い方の秘密
いま人気のアニメ「チ。」のテーマソングでも有名な『怪獣』は、彼らの持つ音楽的世界観を端的に体現した一曲です。
この曲の中には、この曲について知ることでサカナクションが持つ多くの気づきが得られます。
リズムに乗るための「音節のばらし方」
この曲で特に目を引くのは、言葉をただの文章として処理するのではなく、リズムに溶け込ませるように分割して歌っている点です。
たとえばAメロの「この暗い夜の怪獣になっても」という単語も、滑らかに繋げるのではなく、「この暗いよ るの怪獣」というふうに楽曲にあうようにあえて不自然に分割しているのです。
こうして分割することで次にくる「ここに残しておきたいんだよ」という楽曲に「よ」の音が重なるようにもなっています。
これはラップ的なアプローチに近く、韻を踏むといわれています。
1拍の中にあえて余白を持たせたり、逆に詰め込んだりすることで、独特な印象とともにしっかりと韻をふむことができるようになるのです。
独特のテンポ感
最近の音楽は特にグルーブ感を重視するような楽曲が多いですが、『怪獣』ではあえてオンビートにしてグルーブ感を消すような歌い方が目立ちます。
たとえば「だんだん食べる」「何十回も」といった歌詞では、前のほうにリズムがあることで淡々とした音楽の印象を与えます。
まるで何者かが町中を歩き回っているような力強く、しかし怪しい雰囲気を醸し出しています。
オンビートだけとは限りません。
この他にもサカナクションの曲は裏拍で入るような歌い方のときでもテンポにきちっとあったような歌い方をすることで、まるでグルーブ感が消されたような印象で歌うことがしばしばあります。
『新宝島』では裏拍からはいるような歌い方ですが、その裏のリズムですらテンポに忠実にリズムの網目にきれいに配置されています。
メトロノームを鳴らしながら歌っているような正確なテンポ取りはまさにサカナクションらしい歌い方の特徴でもあるでしょう。
歌詞に込められた視点と思考の面白さ
サカナクションの楽曲において、歌詞の存在は非常に大きな意味を持ちます。
『怪獣』の歌詞では「何十螺旋の知恵の輪」や「この世界は好都合に未完成」など、肯定的な言葉と否定的な言葉を組み合わせた上で、明るくも暗くもないコード運びで聞き手の不安感と高揚感をあおり緊張感をもって楽しませ続けます。
この歌詞の魅力を最大限にいかすのが特徴ある山口一郎さんの歌い方なのです。
つまり歌詞の深みを知ることによって、歌い方を読み解いていくこともできるようになるのです。
風景描写と抽象のバランス感覚
サカナクションの歌詞では、抽象的な感情と具体的な風景が巧みに混ざり合っています。
怪獣の歌詞で
「点と線の延長線上を辿るこの淋しさも 暗がりで目が慣れる頃にはもう忘れてるんだ」
とあるように、はじめに抽象的な「点」と「線」の話からはじまり、「暗がりで目が慣れる頃にはもう忘れてるんだ」という具体的な実生活にありそうな話に落ち着いていきます。
このバランスは、歌唱にも影響します。
共感できそうな具体的な情景でこそ山口一郎さんは声を荒げません。
絶妙に配置された言葉のバランスを保つように、また引き立たせるように声自体に力を入れないのです。
言葉の意味に引っ張られず、しっかりと
聴き手に委ねる余白のつくり方
歌詞を読むだけでは意味が捉えきれないような「余白」もサカナクションの魅力です。
たとえば、「何も語らずただそこに立っているだけの登場人物」のような描写。
明言されないからこそ、聴き手はそこに自分自身の感情や経験を投影する余地が生まれます。
歌う際にもこの「余白」は大切で、全てを説明しすぎないニュアンスを込めることで、聴き手の想像力を引き出すことができます。
この感覚は演技的というよりも、「詩を読む」ようなスタンスに近いかもしれません。
サカナクションの歌声に共通する特徴とは
サカナクションのボーカル・山口一郎さんの歌声には、非常に個性的な要素がいくつもあります。
単に「高い」「太い」と言った指標に収まらない、独自のその歌声の特徴を3つの観点から見ていきましょう。
声の芯とエアーのバランス
まず特筆すべきは、「芯」と「エアー」の絶妙なバランスです。
山口さんの声は、どんなに柔らかい表現をしていても、決して「ぼやけない芯」が存在します。
一方で、強く出しすぎると「押しつけがましく」聞こえてしまうところを、吐息のようなニュアンスで空気を多めに混ぜて歌うことで、うるさすぎない印象を与えています。
こういったテンポにきっちりと合った歌い方はときに機械的に聞こえてしまいますが山口一郎さんにはそれがありません。
それは絶妙な息と声のバランスで世界観を作っているからできることです。
「ささやくように歌っているのに芯がある」という状態を実現するためには、喉を締めずに息と声を同時に乗せるスキルが求められるのです。
リップロールや地声発声の練習をすることで、太く、しかし響きのある柔らかな印象を与えることができます。
「抜く」ことで出る浮遊感と情緒
もう一つのポイントは「抜き」の技術です。
たとえば、サビで感情を爆発させるようなタイプのボーカリストと対象的に、山口一郎さんはむしろ、一番盛り上がるところで「すっと抜く」ような歌い方をします。
この技術を習得するには、感情的になりすぎず、フラットな意識で音の高さ・タイミングをコントロールする必要があります。
サカナクションの曲をためしにサビで声を張り上げて歌ってみてください。
曲とあまりマッチしないことに気づくと思います。
このことからも歌い方がフラットであるというのが一つ技術として特徴的だとわかるでしょう。
歌詞の構成と歌唱の関係
とくに「怪獣」に限っては、その独特の楽曲の構成からも、歌をひもとくことができます。
まず冒頭にサビと思わせるメロディから、Aメロ、Bメロのようなメロディ。
そして冒頭サビかと思っていたメロディとは違うメロディで盛り上がるメロディ。
山口一郎さん自身はこの区分けをAメロ、Bメロのような形ではなく「ブロック」と呼んでいます。
細かく整理するとメロディと与える印象の効果は以下のようになっています。
ブロック1(サビ的効果)→ブロック2(Aメロ的効果)→ブロック3(Bメロ的効果)→ブロック4(サビ的効果)→ブロック1(Aメロ的効果)→ブロック2(Bメロ的効果)→ブロック3(Bメロっぽい曲)→ブロック4 ※最初のブロック1の伴奏で歌う
こうして文字で整理するとよりその複雑性がわかるかと思います。
※動画で本人の解説をみるともっとわかりやすいので、みてみることをおすすめします。
伴奏が変わる中で世界観を保つためにその構成にあった歌い方をしているのです
このように「Aメロ、Bメロ、サビ」という典型的な形にとらわれないながらも、そこに腹落ちする展開を生み出し、さらに歌唱を工夫することによって見事に世界観を描き出すことに成功しています。
これこそがサカナクションのすごさだと言えるでしょう。
初心者・上級者それぞれの意識ポイント
サカナクションの歌い方は、その洗練されたサウンドや詞の世界観から「難しそう」と感じられがちです。
ですが実際には、初心者でも楽しめるポイントと、上級者が挑戦できる深みの両方を併せ持っています。
初心者はまず「音程とリズムの分離」を意識
初心者がサカナクションの楽曲を歌う場合、まず最初につまずきやすいのがリズムです。
一定に正確に続けられるサカナクションのリズムは初心者にはあわせにくい印象を与えます。
「正しい音程を追っているのに曲にならない」
そんなときはまずリズムからアプローチするといいでしょう。
まずリズムに合わせて歌詞を読み上げる練習をすること。
歌う前に“語る”ことで、言葉のテンポやタイミングを身体で覚えることができます。
音程はその後に乗せていくと、自然に曲のリズムにあわせていくことができます。
上級者は「声の質感」に挑戦
ある程度歌に慣れてきたら、次に挑戦したいのは声の質感をどう演じ分けるかです。
サカナクションの曲は初心者にも歌いやすいような印象があります。
それは一定のリズムが取れればあとは音程をあわせるだけでいいような印象があるからです。
しかし実際には歌う声の質感を使い分けている高度な楽曲です。
ソロでうたう冒頭の部分は声が映えるように音程にしっかりアプローチしたぱきっとした歌声を、逆に迷路に迷い込んだような不安定な音程のときにはそこに感情をひっぱられないように、響きをよくしつつも淡々と、しかしウィスパーボイスなどのテクニックを随所に差し込んで聞きやすくしています。
NOPPOミュージックではサカナクションの楽曲に特化した練習ができる!
NOPPOミュージックではサカナクションの歌い方を習得したい!そんな人に向けてカラオケの設備が完備しているレッスンルームで、ひとりひとりに合ったカリキュラムで練習することができます。
サカナクションの「怪獣」の歌い方をみっちり1ヶ月かけて練習したい!
そんなことも可能です。
まとめ:適切なアプローチで曲を歌いあげられる!
いかがだったでしょうか?
サカナクションの歌い方は、単に高音を出すとか、感情を込めるという枠を超えて、言葉のリズム・空気感・引き算の美学など、非常に多面的な要素で成り立っています。
初心者の方もまずはリズムに合わせて語るように歌うことから始めてみてください。
そして、慣れてきたら、徐々に高度な表現にも少しずつ挑戦していきましょう。
どんなレベルの方でも、サカナクションの歌は必ず「新しい発見」があるはずです。
ぜひ、あなたの声でその魅力を体感してみてください!
NOPPOミュージックでサカナクションの曲を楽しく歌えるようになろう!
大宮のボイトレスクール「NOPPO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!